社内規程作成・見直し
弁護士による社内規程のチェックは、残業代請求などのトラブル防止策の一つです
「社内規程は10年前の会社創業以来、見直していないが大丈夫ですか?」
「当社にはそもそも就業規則がないが、作成したほうがいいのだろうか?」
このように、就業規則などの社内規程を作成しよう、見直そうという経営者の方が増えてきています。
解雇や残業代請求などのトラブルを避けるためにも、小規模の会社(従業員10人未満)であっても、就業ルールの定めである就業規則は最低限整備したほうが良いでしょう。
また、労働関連法にも改正はありますので、一度策定した規程であってもアップデートは必要です。
なお、就業規則のほかにも、給与規程、退職金規程、出張旅費規程、育児休業規程等などの諸規程も必要に応じて作成したほうが良いものもあります。
社内規程の作成や見直しを図る際は、ぜひ弁護士にご依頼ください。
以下、中小企業でよく見られる「社内規程作成・見直し」の問題をQ&A形式で解説します。Q部分をクリックすると回答を見ることができます。
労働基準法上、常時10人以上の従業員を雇用すると、使用者(雇主)は就業規則を作成して労働基準監督署長に届ける必要があります(同法89条)。
この10人に入る従業員は、正社員かパートタイマーなどの名称は問いません。
しかし、繁忙期の一時期のみのアルバイト、また労働契約のない下請労働者や派遣労働者などは含まれません。
貴社の場合は、従業員が10人未満ということですので、法律上、就業規則の作成は義務付けられていませんが、解雇や残業代請求などのトラブルを防止するため、就業規則を作成しておくのが望ましいでしょう。
A.従業員が1人であっても「36協定」は必要です。
労働基準法では、1日8時間、もしくは週40時間を超える労働を禁止しており、これを超えて労働をしてもらうには、使用者(雇主)と事業所の労働者の過半数代表により「36協定」を締結し、これを労働基準監督署長に届出をする必要があります。
当該協定の届出をせずに時間外または休日労働をさせた場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
「労働契約法」10条が定める要件を満たした場合、就業規則の変更により賃金カットは可能です。
賃金は就業規則の規定事項ですので、賃金の一律カットは就業規則の「不利益変更」に該当します。
このような場合、労働契約法10条が定める要件を満たした場合に、就業規則の変更により、労働条件を不利益に変更することが可能になります。
この要件とは、
・変更後の就業規則を従業員に周知させること、
・その変更により従業員が受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであること
が必要になります。
特に、上掲の2つ目の要件については判断が難しいと思いますので、 弁護士に相談しながら進めましょう。
法律上は、退職を従業員から申し出るのは、2週間前の意思表示でよいので、2か月前と定めるのは、あくまでも会社の希望する時期を規定するに過ぎません。
期間の定めのない労働契約の場合、従業員が辞職の意思表示をすれば2週間の経過をもって自動的に終了します。
また、期間の定めのある労働契約の場合でも、やむを得ない事由があるときは退職自体は認められており、その終了については同様に考えられます(ただし、後者については損害賠償の問題は別途残ります)。
このように、法律上は、退職を従業員から申し出るのは、2週間前の意思表示でよいわけです。
したがって、2ヶ月前と定めるのは、あくまでも会社の希望する時期を規定するに過ぎず、仮に従業員が申し出から退職までの間が2ヶ月より短いケースでも、従業員の希望日に退職を認めるという扱いをしなければなりません。
有給休暇買い上げを就業規則に規定することはできませんが、次年度繰越しは就業規則に規定することができます。
有給休暇の買い上げは、労働基準法上、禁止されていると解されています。
したがって、有給休暇の買い上げを就業規則に規定することはできません。
なお、従業員が有給休暇を取得せず、時効や退職等で消滅するような場合、残日数を買い上げることは必ずしも同法で禁止されているとは解されていませんが、有給休暇の取得を抑制することになるのは望ましくないため、このような規定は設けないほうがよいでしょう。
また、ある年度に取得しなかった有給休暇については、次年度に繰り越すことができると解するのが一般的です。
したがって、会社としては未消化の有給休暇の次年度繰越を認めるべきですので、就業規則に定めることは何ら問題ありません。


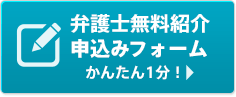

 困った時すぐに”専門家”に相談できる安心感は、経営者としての自信につながります。
困った時すぐに”専門家”に相談できる安心感は、経営者としての自信につながります。 「中小企業向け」+「顧問料1万円」で探し当てた顧問弁護士は、当社にとってもう必要不可欠な存在です。
「中小企業向け」+「顧問料1万円」で探し当てた顧問弁護士は、当社にとってもう必要不可欠な存在です。